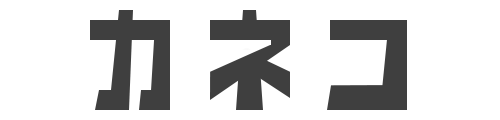-
デジタル補聴器ってなに?(基本性能)
-
以前の補聴器は、入ってきた音を大きくするだけでした。ただ大きくするだけなので、大きくする必要のない音(聞こえている音)まで大きくしてしまい、うるさくて使えないという結果に終わることが多かったようです。
現在の補聴器は小さなコンピュータです。使用者の聴力を測定して入力、設定を終えると、補聴器は使用者に向かってくる人の声を大きくしようとします。細かく言うと、聞こえにくい音、例えば高音が聞こえにくいなら高音を、低音なら低音を大きくして、人の声を大きくしようとします。
補聴器が必要な音と判断した音、例えば危険を察知するための音は小さくしません。車や自転車の等がそれにあたります。
不要と判断した音、例えば低音の連続するエアコンや扇風機の音、高音の強い音(突発音)を伴う食器を洗うガチャガチャ音や足音音、ドアの開閉音は小さくします。
さらに最近の補聴器は左右で通信をしています(両耳装用の場合)。文字通りの離れ業ですが、この機能で音の来る方向を判別して周囲の状況をわかりやすくしています。補聴器の苦手な面として、補聴器は自分に向かってくる人の声を大きくしようとしますから、複数の人の声が入り乱れている環境を苦手としています。大きい音に囲まれた状態での小さい音や声も大きくできません。カラオケを想像してください。大きい声で歌っている人がいて、近くの人が話しかけてきても聞き取りづらいです。補聴器が必要でない通常の人でも聞き取りづらい状態は、補聴器をつけてもやはり聞き取りづらいのです。
-
補聴器の形について - 耳掛け型と耳穴型
-
補聴器の形として耳掛け型と耳穴型の二つに大別されます。それぞれ特徴があるので説明します。
・耳掛け型 耳にかけてチューブ等で耳に入る耳栓とつなげて音を届けます。耳穴型に比べて大きいですが、対応する聴力の範囲が広いのと、出力が大きいのでハイパワーが必要な場合は耳掛け型一択です。大きい分電池交換等の取り回しがしやすいです。風の強い場所では風切音がすることがあります。耳栓の代わりに耳穴型を採取して専用のイヤーモールドをつけることができます。慣れるまでは付け外しに練習が必要です。大きい大きいと書きましたが、最近の物は耳の後ろに隠れてしまうほどの小型のものもあります。
・耳穴型 小さく目立ちにくい補聴器です。超小型の物だと付けていることがわからないほどです。耳の中に入れるので風切音は少なく、メガネやマスクと干渉しません。小さいのが特長ですが、両耳の場合形が似ているため、装用の際に左右の間違いと、耳に入れる向きの注意が必要です。しっかりはまっていないと落とす可能性があり、落とした場合目立ちにくいゆえに見つかりにくいです。小さいが故に電池交換が不便かもしれません。耳掛け型に比べて出力が小さいので、聴力によってはお勧めしないこともあります。
耳穴型は耳穴の形を採取して補聴器の型を作るのですが、耳穴は年々形が変わっていくので、年数がたつと型が合わなくなり、ピーピー音(ハウリング)がすることがあります。その場合、型を作り直すか、買い換えが必要になることもあります。個々の特性によってもお勧めする補聴器の形は変わってきます。どちらの補聴器も装用や電池交換に慣れるまでは練習が必要です。当店では装用や電池交換の練習にそれなりに時間を取っていますが、ご自宅でも練習が必要かと思います。
-
補聴器の色ってベージュじゃないの?
-
昔は補聴器をつけることは恥ずかしいという文化だったのか、少しでも目立ちにくいという意味でベージュの色一択でした。それなりに大きかったので耳の上で存在感を主張していました。補聴器の進化とともに小型で目立ちにくいものに成長しました。
一方で補聴器先進国であるヨーロッパの国々では、補聴器を見せることでおしゃれをするという文化のようで、カラフルな色が揃っています。
その影響を受けてか最近の補聴器では、ブルーやレッド、グリーンなど機種によりますが色のバリエーションが豊富です。現在ベージュを選ばれる方は少数で、シルバー、ブラウン、ブラック、が多いかな?と思います。
-
何色が人気なの?
-
さまざまです。(^^;
耳掛け型で目立ちにくい色の選び方としては、髪の色に合わせるという方法があります。髪色が黒なら補聴器も暗色系、シルバーなら白色銀色系等です。
逆に明るい色を選ぶ方は紛失時にすぐわかる、周りの人がつけているか(つけ忘れているか)わかりやすい、という理由が多いです。デイサービスで落としてもすぐ見つけてもらえた、畑作業で落としてもすぐ見つかるように…(畑作業での使用は落としやすいのでお薦めしにくいですが)。
左右で色を別にした方もいらっしゃいます。手が不自由でご家族がつけてあげるときに左右で色を別にしてわかりやすくしたそうです。
-
いやいや補聴器なくても聞こえてるよ?
-
年齢を重ねることによる聴力低下は徐々に進むので、ご本人は聴力の低下を気づいていない場合もありますし、まだ補聴器に頼りたくないという心情もあるかと思います。ご家族といっしょに来店されるお客様の半分ほどの方がこのように認識していると思います。よく聞こえない状態は、会話が成り立たない、テレビの音が大きすぎる等、ご本人にとってもご家族にとってもいい状況とはいえません。聴力測定で度合いがわかりますので、お気軽にご相談ください。聴力測定、相談、お試し体験までは無料ですし、無理に販売することはありませんから、ご安心ください。
-
補聴器はいつからつけたらいい?
-
聴力の低下に気づいてから補聴器の装用までにかかる年数を調べたところ、平均で8年(軽度の方だと12年)放置されていたという研究結果があります。それだけ長期間に渡って少しずつ聴力低下が進むので、聞こえない事に慣れてしまうのが問題だと思います。実際ご本人はもとより、ご家族がなんとかしたいとの思いも見受けられます。
年齢による聴力低下は、高齢になればなるほど長い間聞こえないことに慣れてしまっているので、補聴器の音に慣れるまではうるさく感じる方が多いです。装用や取り扱いについても同様ですし、声が聞き取りづらくなって何回か聞き返したり、テレビの音を大きくしないと聞こえない、また、ご家族の指摘があった等の気づいた時期が検討の時だと思います。
聴力の低下は30代からはじまっています。聞こえにくい、は決して特別なことではなく、誰にでも起こる可能性があります。
-
つけ外しは簡単?
-
当店では、貸出機を渡す際、またご購入の補聴器をお渡しする際、それなりに時間をかけて練習していただいております。ちゃんと耳にかかっている、耳穴にはまっている状態でないと補聴器の効果が半減するどころか、落として紛失の原因になってしまうからです。
耳掛け型の場合
・左右を確認して・耳にかける・耳栓を耳に入れる
耳穴型の場合
・左右を確認、上下に注意して耳に入れる
と文章で書くと簡単ですが、慣れるまでに時間がかかる方もいらっしゃいます。耳に入れるときに鏡を使っても耳元が見にくいため、本体の向きが分かりにくいのが原因です。腕が耳まで上がらない方もいらっしゃいますし、取り扱いが習慣化してしまえば問題ないのですが、ご高齢の方の場合習慣になるまで時間がかかる事もありますし、高齢で独居の方で習慣までに至らなかった方もいらっしゃいます。ご家族さまも補聴器の取り扱いや装用の方法はご理解いただいた方がよろしいかと思います。
-
デジタル補聴器の寿命は何年くらい?
-
環境や使い方にもよりますが、平均で5年くらいでしょうか。きちんとお手入れやメンテナンスをしながら、10年近く使っている方もいます。補聴器はデリケートな精密機械です。防水性能もありますが、汗などは徐々に内部に浸透していきます。より良い状態で長くお使いいただくためには、夏の汗や汚れをを使用後に拭き取るなどの日常的なお手入れの他に、定期的にメーカーに内部クリーニング&点検に出す、場合によっては部品交換などのメンテナンスが大切です。
-
10年使えるなら頑張りたい!
-
ご購入いただいたものを長く使っていただくのはとても大切な事ですので、お手伝いさせていただきます。
一方、補聴器の技術は年々進歩しています。10年前の補聴器と現在の補聴器は別物と言っていいほど進化しています。現在の低価格の補聴器でも、過去高価な一部の補聴器より性能がいい、とメーカーが言うほどです。メンテナンス費用も都度かかりますし、メーカーの修理対応期間の問題もありますので、ある程度の期間での買い換えをお勧めします。
-
新聞やテレビ広告の補聴器は安いよ?
-
基本的に安く売られている補聴器(集音器)は、音量の調節ができる程度で、細かい音質の調整ができません。もちろん音の大小で満足される方もいらっしゃいますので否定するわけではありませんが、大抵の方は音を大きくすると今まで気にならなかったエアコンの音、扇風機の音、食器を洗う音などが気になってしまう、結局音を小さくしないと使えない、ほんのちょっとの事なのになんとかならないのか?と感じられるようです。
上記の問題は補聴器の性能としては基本的なもので、当店で扱う低価格の補聴器でもこの効果は高いです。
一般的に高い補聴器になればなるほど音質の調整が細かくできますので、お客様によって求められる性能の機種を検討いただければと思います。
こちらの解説もご覧ください。
-
両耳だと高いし、片耳でもいいよね?
-
メーカーは両耳使用を推奨していますが、片耳で使う方もいらっしゃいますし、ご満足いただいている方が大半です。
メガネで置き換えてもらえばわかりやすいと思うのですが、例えば片目だけレンズを入れると見やすくはなりますが、片目だけよく見える状態だと疲れてしまいます。補聴器を着けていない側の耳では聞こえにくい上に疲れやすく、補聴器の基本性能である音の方向の判別も限定的になります。
音の方向がわかるということは意外と重要で、車の動きや距離感がわかりやすくなりますし、聞き取りにも影響します。
価格的にお勧めしにくい場合もありますが、お試し機で体験していただくのが一番かと思います。
先に片耳だけ購入いただいて後日もう片耳をご購入いただくことも可能です(片耳ご購入から短期間でしたらお支払いを両耳価格にできます)。
-
長く使うために気をつけることは?
-
やはり一番大事なのは日常のお手入れです。毎日お手入れをすることでより長い期間使用していただけます。
〇水分や汗
補聴器の故障で圧倒的に多いのが汗や水分が補聴器内部にしみこんでおきる金属部分のサビや腐食、合わせて長期間使用によるコンピュータ部分の劣化です。
特に夏場は補聴器と耳が密着し、常に汗で濡れている状態です。
補聴器は強力な防水性能がありますが、電池の出し入れ口や耳穴につながるチューブやワイヤの根本など可動部分や接続部分から少しずつ汗や水分、汚れが入り込みます。
夜取り外したらそのまま放置せず、すぐに補聴器本体の水分と汚れを拭き落として下さい。その際、電池を取り外して電池ドアの内側も水分も確認し除去するようにしてください。
その後乾燥ケース入れて乾燥させるようにしてください。
〇耳アカ
もう一つ大事な注意点として耳アカがあります。
実は耳アカも聞こえに大きく影響するものであり、補聴器の耳穴部分に詰まって音が出なくなることがあります。補聴器本体の耳穴部分には耳アカが本体に入り込まないような部品がついていますが、ほっておくとその部分に耳アカがこびりついて塞いでしまうので、お手入れグッズの耳穴ブラシで耳アカを落とす、ご来店時の調整やクリーニングで耳アカを取り除く等の必要があります。
それまで耳アカはそんなに出なかった方でも補聴器をつけるようになってから耳アカが出るようになった方もいらっしゃいます。耳が補聴器を異物と判断して耳アカで押し出そうとしてるのではないか?(メーカー談)とのことですが、定期的に耳鼻科へ通院して耳の総合的な状況を確認してもらうのは必要だと思います。
以前補聴器を購入に来たお客様で両耳耳アカで詰まって会話ができない方がいらっしゃいました。耳鼻科通院を勧めたところ、後日来店されて耳アカ取ったら聞こえるようになって補聴器いらなくなっちゃったと報告されました…よかったですorz(補聴器販売あるあるです)
-
空気電池のはなし
-
補聴器に使用する電池は空気電池といいます。ボタン電池と形状は似ていますが仕組みが違い、腕時計や家電製品のリモコンに使うボタン電池と比べて出力が大きいです。
補聴器用の空気電池は電池の大きさによって色分けされていて、青、オレンジ、茶色、黄色の4種類あり、この順で小さくなります。これはどのメーカーでも共通で、同じ色のパッケージの電池を買えばいいので、出先で急に電池が必要になっても色さえわかればお近くの電気店やドラッグストアで手に入ります。未使用時の電池には片面にシールが貼ってあります。
シールを剝がすと小さな穴が3つ空いていて、そこに空気が入ることで放電を始めます。また穴を塞げば、穴に入った空気がなくなった時点で放電が止まるのでそのまま保存できそうですが、微妙に空気が入ってくるのか長期の保存はできないようです。一度シールを剥がした電池は早めに使い切るようにしましょう。
電池の寿命は使用環境によりますが、1週間から2週間ぐらい、10日ぐらいが標準なように思います。
電池の電圧が下がってくると補聴器が音声でお知らせします。お知らせから数時間で電池切れするようなので、お知らせが聞こえたら早めに電池交換をするようにしましょう。
電池交換する日を決めて、電池切れを起こす前に先に交換してしまうのも一つの方法です。空気電池は冬場に弱いです。具体的にいうと、・低温 ・乾燥 ・二酸化炭素の増加(ストーブやファンヒーター)の影響を受け、電池寿命が35%ほど短くなることがあります。保管の際は補聴器本体とは別にし、乾燥機や乾燥ケースに入れないようにしましょう。本体を入れる乾燥ケースには、フタの上部に磁石パッドがついているので、外した電池を張り付けて保管できるようになっています。空気電池の適温は15℃~20℃くらいですので保管は常温、冬場は暖かい部屋がよいです。
冬の朝方は部屋の温度も下がっています。空気電池も低温だと電圧が低下していて性能を発揮できないので、手で暖めてから使用するとよいようです。。
-
補聴器をつけても自分の声がこもって聞こえないけどなんで?
-
耳を指でふさいで声を出すとこもって聞こえます。補聴器も耳をふさぐような構造なのにこもって聞こえません。
耳掛け型の耳栓は、標準の物は耳をふさぐ形ですが、隙間部分を大きくして音の通りをよくしたりして、こもり感を減らすようになっています。
耳穴型や耳掛け型のイヤーモールドの場合、耳の外と中を通す穴を開けてあり(ベント、貫通してない場合もある)、こもりや閉塞感を減らすようになっています。
小さい穴なのであまり意識されるものではないですが、聞こえにはかなり影響があります。
-
ピーピー音がする
-
ピーピー音がすることをハウリングといいます。補聴器に限らずオーディオ機器は、マイクから入った音を大きくしてスピーカから出します。
このときに出た音が再度マイクから入って音を大きくして…を繰り返した結果ピーピー音がします。補聴器を手に乗せてもう片方の手で上からかぶせたり、箱に閉じ込めたりするとピーピー音がなります。
ピーピー音がすることは機械的には正常です。例えば電源を入れての装用の時は時々鳴りますし、車に乗っているときに耳を窓に近づけると鳴ったりします。上記以外で鳴るようだと、補聴器の機能としては邪魔になってしまうため、現代の補聴器はハウリングの抑制機能がついています。調整時に全体の音量を上げたときに鳴ることがあります。その場合はその成分の周波数を下げるなどの対処をします。
話したり、食事の時の口の動きに合わせて鳴るようになった場合は、耳栓やイヤーモールドを作って長期間がたつと耳穴の形が変化して耳との間に隙間ができるようになったかもしれません。その場合、イヤーモールドや耳型を作り直す方法があります。現代の補聴器ではハウリングしたまま使っている人を見かけません。ちゃんと抑制機能が働いていて、調整もされているのだと思います。
その昔は耳からピーピー音をさせたままの方がいらっしゃいました。ずっと鳴っていてうるさくないのかな?と思っていたのですが、この仕事に就いてわかりました。どうやらご本人にはその音(高音)が聞こえていないらしいです。
-
補聴器をつけてさらに耳が悪くならない?
-
大きい音が耳を悪くしないか、という心配でしたら、補聴器には出力制限機能がついています。調整された補聴器であれば、必要以上に大きな音は出ないようになっていますので心配はありません。
補聴器をつけると聴力がさらに下がるのではないかという意味でしたら、ご自身に合わせて調整された補聴器を正しく使用していれば聴力が低下することはありません。補聴器の調整があっていないとか、人から譲ってもらった補聴器を再調整せずにそのまま使っていて必要以上に大きい音で使用していた場合は聴力が低下してしまうこともあります。
聴力は体調によって変わることもあるので定期的に耳鼻科で診てもらうことも大事です。聴力が変わっても補聴器を調整すれば最適な状態で使い続けることができます。
-
補聴器は落としやすい?
-
残念ながら落としやすい、無くしやすいと言わざるを得ません。落とさない無くさないための注意と工夫が必要です。
注意としては、ちゃんと装用できていれば簡単に外れません。逆にしっかり耳にはまっていないと落ちる原因となります。耳掛け型の場合、有料ですが耳栓の代わりに耳穴の形を採取して作るイヤーモールドをつければさらに落ちにくくする効果はあります。
工夫としては、当店で補聴器をお買い上げの方にはサスペンダー(補聴器に取り付ける落下防止の紐)を差し上げています。このサスペンダーを付けていて落とした方は今のところいませんが、どうやら外している時に落としてしまうようです…色を目立つ色にするのも方法の一つですが、残念ながら万能な方法がないのが現状です。
紛失保証がつく補聴器が多くなってきましたが、主に高価格帯の機種です。最近では低価格帯でも有料で紛失保証をつけることもできるようになってきました。ご相談ください。
-
納期はどれくらいですか?
-
耳掛け型でしたら翌々営業日、耳型を採取して作る耳穴型や耳掛け型にイヤーモールドを作る場合、2週間ほどの時間がかかります。