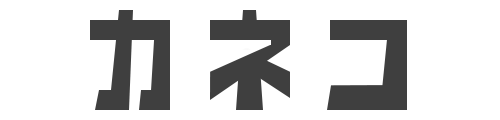骨伝導補聴器について説明します。その前に、音の聞こえ方(聴力)について気導と骨伝導の違いを説明します。
気導聴力とは?
気導聴力は、音波が空気を伝わって耳に入り、鼓膜を振動させることで音を聞く能力を指します。
私たちが普段耳で音を聞くときに使われる一般的な聴覚経路です。
仕組み:
- 外耳から音波が入る。
- 音波が鼓膜を振動させる。
- 鼓膜の振動が耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)を通じて内耳へ伝達される。
- 内耳(蝸牛)で振動が電気信号に変換され、聴神経を通じて脳に伝わる。
特徴:
- 空気を介して音が伝わるため「気導」と呼ばれる。
- 聴覚検査ではヘッドホンやイヤホンを使用して音を聞かせ、気導聴力を測定する。
影響を受けやすい障害:
- 外耳や中耳に問題がある場合(耳垢の詰まり、中耳炎、鼓膜損傷など)は気導聴力が低下する。
骨伝導聴力とは?
骨伝導聴力は、音波が頭蓋骨を振動させることで内耳に直接伝わり、音を聞く能力を指します。
鼓膜や耳小骨を通らずに内耳に音が届くため、通常の聴覚経路とは異なる方法で音を感じます。
仕組み:
- 音波が頭部の骨に振動を与える。
- 骨の振動が直接内耳(蝸牛)に伝わる。
- 内耳で電気信号に変換され、脳に伝達される。
特徴:
- 耳栓やイヤホンで耳をふさがないために蒸れない、異物感がない。
- 耳の穴の大きさに依らない。イヤホンが抜けてくる等がない。
- 耳をふさがないため周りの音も聞こえる。
- 自分の声が響いて聞こえるという事がない。
- 鼓膜や中耳を介さないため、外耳や中耳に問題があっても音を聞くことが可能。
- 聴覚検査では、骨振動機(骨導振動子)を頭や耳の後ろに当てて測定する。
- メガネ型やヘッドホン、ヘッドセット型が多い(振動部を骨に押し当てるため)
骨伝導が特に役立つ場合:
- 中耳や外耳の障害による伝音難聴がある場合。
- 通常の気導を使った補聴器が効果的でない場合。
- 工事現場などの騒音の多いところで、必要な音声を聞き取ることができる
気導聴力と骨伝導聴力の違い
| 項目 | 気導聴力 | 骨伝導聴力 |
|---|---|---|
| 音の伝達経路 | 外耳・中耳・内耳を経由 | 頭蓋骨を通じて直接内耳へ |
| 検査方法 | ヘッドホンやイヤホンを使用 | 骨導振動子を使用 |
| 影響を受ける障害 | 外耳や中耳の問題 | 内耳や聴神経の問題 |
| 利用場面 | 一般的な音の聞き方、補聴器など | 骨伝導補聴器や特殊な聴覚支援機器 |
気導聴力の場合、音の空気振動が遮られると伝わらないため、外耳や中耳の病気で物理的に耳穴が塞がると音が伝わらない事になります。
同様に骨伝導聴力の場合、骨を通して音を振動させて伝わるため、耳が塞がっているいないにかかわりません。その先の音を検出する聴神経や脳に問題がある場合、音として認識できない事になります。
骨伝導補聴器は今までの補聴器よりよく聞こえる?
ここまでの説明から骨伝導補聴器は、特に外耳や中耳の障害を持つ方や、通常の補聴器が合わない方(伝音性難聴)にとって、有効な選択肢になります。
- 外耳や中耳に問題がある(伝音性難聴)
- 骨伝導聴力が有効な値であること
それでは今までの(気導)補聴器をお使いの方が、骨伝導補聴器でさらに良好な結果になるのかどうか。
通常加齢に伴う聴力の低下は、感応性難聴(又は混合性難聴)に分類される方が圧倒的です。
ですので、今まで通常の補聴器を使われていた方が骨伝導補聴器に付け替えてよりよく音を聞こえるようになるかというとそうではなさそうです。
通常加齢に伴う感応性難聴の方の場合、気導聴力が低下している場合、骨伝導聴力も同様に低くなっている方が一般的です。
あくまで骨伝導聴力が有効な値の方でしたら効果がある、ということになるかと思います。
骨伝導の課題
骨伝導の今後の課題として以下があげられます
- 骨伝導部を骨に押さえつけるため、圧迫感を感じやすい、圧迫を感じる程度に絞めないといけない。
- ヘッドホン、ヘッドセット型が多いため目立つ物が多い。
- 音質的には問題がある。
補聴器に関して言えば、音質は特に大事な機能なので、まだ技術的に発展途上であるといえると思います。
耳掛け型の骨伝導補聴器も出て来たようです。
今後技術が発展していろんな方法の補聴器ができるといいなと思います。